事業運営のための衛生工学知識を深め、また、労働衛生コンサルタントを目指す方の参考になるよう、衛生工学の知識と新しい法令の告知情報を中心に記載していきます。
皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアル(令和5年11月暫定版)公開されています。 [行政ニュース 化学物質管理]
皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアル(令和5年11月暫定版)
厚労省の「新たな化学物質管理」のまとめページに、ひっそりと、『皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアル(令和5年11月暫定版)』が公開されています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099121_00005.html

根拠法令の他、解説やコラムなど、図表も多くて分かりやすいと感じました。
内容が複雑なので、それでも、難題だなと思いますが。

目次は、こんな感じです。

目次
第1章 労働安全衛生法関係政省令改正(令和4年改正)の概要 .
労働安全衛生法関係政省令改正全体の概要
皮膚等障害化学物質等への直接接触の防止
皮膚等障害化学物質等の考え方
特別規則対象物質
皮膚刺激性有害物質
経皮吸収と皮膚吸収性有害物質
保護具着用管理責任者の職務
第2章 皮膚障害等防止用保護具に関する基礎知識
皮膚等障害発生の現状
皮膚等障害化学物質等による労働災害事例
皮膚障害等防止用保護具の種類
化学防護手袋 .
化学防護服(保護衣)
保護めがね .
化学防護長靴(履物)
化学防護手袋における性能の考え方
第3章 化学防護手袋の選定
選定の基本的な考え方
化学防護手袋の選定 .
作業等の確認 .
化学防護手袋のスクリーニング
製品の性能確認
保護具メーカーへの問合せ .
まとめ
第4章 化学防護手袋の使用
使用前の留意点
使用中の留意点
使用後の留意点
第5章 化学防護手袋の保守・管理
保管時の留意点
廃棄時の留意点
第6章 参考資料・データ
※1:図中の皮膚刺激性有害物質は令和5年3月31日までに分類された、政府によるGHS分類の結果に基づく。
※2:図中の物質数は原則CAS登録番号単位。
※3:図中の物質数は令和5年8月4日時点のもの9であり、原則として年1回更新される見込み。
にほんブログ村
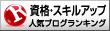
資格・スキルアップランキング
「化学物質管理検討会情報」個人ばく露測定に係る測定精度の担保について [行政ニュース 化学物質管理]
「化学物質管理に係る専門家検討会」の中間取りまとめが公表されました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36401.html
個人ばく露測定※に係る測定精度を担保するための方策について取りまとめたものです
ポイントは「個人ばく露測定に係る測定精度の担保等について」
① 基本的な考え方
② 個人ばく露測定を行う者に求められる能力
③ 想定される資格者の要件
を定めたものです。
どうやら、「資格者による個人ばく露測定を義務付ける」方向でまとまったようです。
対象物質が、リスクアセスメント対象物質全体に広がることから、測定機関や測定者のマンパワー不足が懸念されることもあり、作業環境測定士のような資格試験合格者ではなく、講習の修了者としたい旨で、提案されるようです。
但し、作業環境測定のC測定、D測定とも異なることから、新たな講習が必要になると提言されています。(日測恊が、作業環境測定士講習に変わる新たな役割で、さらに発展するような方向性ですね。)
【1】
①金属ヒュームに代表される、特化物の個人ばく露測定
②特別則で作業環境測定を行い、第三管理区分となった場合の個人ばく露測定
については、特別則を改訂して、資格者による測定を義務付ける。
【2】
リスクアセスメント対象物質の個人ばく露測定についても、
ガイドライン等の改正により、資格者による測定を義務付ける。
これからパブコメもあるようですが、検討会メンバーには、化学物質の製造事業者メンバーが居ないようなので、実施に当たっては、必要な技術や原資(人・金)について幅広い議論が必要なように思います。
にほんブログ村
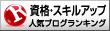
資格・スキルアップランキング
リスクアセスメント対象物質の裾切り値についての告示と通達 [法令・通達情報※労働衛生]
新たな化学物質管理に関して、いわゆる裾切り値する通達がいくつか出ています。

こちらは、表示通知対象物資(リスクアセスメント対象物質)の裾切り値についての告示
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H231109K0010.pdf
別表第3(第3条関係)のように、
GHS区分で、裾切り値が概ね判断できるようになったのは、分かり易くて良いですね。
一方で、決め方が乱暴ではないかという意見もあったようですが。
パブコメ結果公示
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=495230147&Mode=1
意見募集結果
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000262248


こちらは、皮膚等障害化学物質の表示通知に関する裾切り値についての通達
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T231110K0010.pdf
ア) 皮膚刺激性有害物質 1パーセント
イ) 皮膚吸収性有害物質 1パーセント
ただし、国が公表するGHS分類の結果、①生殖細胞変異原性区分1又は発がん性区分1に区分されているものは0.1パーセント、②生殖毒性区分1に区分されているものは0.3パーセント)
各メーカーさんのSDS更新が進みますように。
最後まで読んで頂きありがとうございます。 下記のリンクをポチっとクリックして頂けると更新の励みになります。
![]()
にほんブログ村
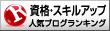
資格・スキルアップランキング
#労働衛生コンサルタント,#口述試験,#試験対策,#労働衛生工学,#筆記試験,#記述式試験



![あなたを守る安全健康保護具ガイド サービス産業で働く人のために [ 田中茂(公衆衛生学) ] あなたを守る安全健康保護具ガイド サービス産業で働く人のために [ 田中茂(公衆衛生学) ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/6902/9784805916902.jpg?_ex=128x128)





![「これからの化学物質管理」 広がりゆく化学物質管理の裾野 [ 化学物質管理士協会 ] 「これからの化学物質管理」 広がりゆく化学物質管理の裾野 [ 化学物質管理士協会 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/7265/9784873267265.jpg?_ex=128x128)
![こう変わる!化学物質管理 第2版[本/雑誌] / 城内博/著 こう変わる!化学物質管理 第2版[本/雑誌] / 城内博/著](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/neowing-r/cabinet/item_img_1717/neobk-2828493.jpg?_ex=128x128)








