事業運営のための衛生工学知識を深め、また、労働衛生コンサルタントを目指す方の参考になるよう、衛生工学の知識と新しい法令の告知情報を中心に記載していきます。
労働衛生コンサルタント試験:過去問「健康管理」令和3年度(2) [法令・通達情報※保健衛生]
問1は熱中症予防ガイドライン(症状・予防法・応急措置)
問2は有機溶剤の健康障害とその防止
問3は健康管理情報の管理
問4はTHP(健康つくり指針)
今日は問2の回答案を考えます。

問題文
問 2 有機溶剤について、以下の設問に答えよ。
(1)有機溶剤の物質としての特性について説明せよ。
(2)職場において有機溶剤にばく露された際の吸収経路と排泄経路について説明せよ。
(3)有機溶剤が体内に吸収された後に、主に分布する臓器あるいは組織を三つ挙げよ。
(4)有機溶剤に共通する毒性を三つ挙げよ。
(5)以下の①~④の有機溶剤は、上記(4)の共通する毒性に加えて、特異的な毒性を有している。それぞれの有機溶剤の特異的な毒性(健康障害)を列挙せよ。
① 二硫化炭素
② ノルマルヘキサン
③ ベンゼン
④ メタノール
(6)有機溶剤には、有機溶剤中毒予防規則において「第三種有機溶剤等」に分類されるものがある。その性状を説明し、該当する有機溶剤の例を一つ挙げよ。
(7)有機溶剤には、特定化学物質障害予防規則において「特別有機溶剤等」に分類されるものがある。
① 「特別有機溶剤等」に分類される有機溶剤に共通する健康影響は何か。
② 「特別有機溶剤等」に分類される有機溶剤を三つ挙げよ。
(8)有機溶剤を常時取り扱う作業者に対して実施される生物学的モニタリングについて説明せよ。
(9)有機溶剤ばく露による健康影響を予防するための ①作業環境管理と ②作業管理について、それぞれ述べよ。
結構なボリュームですね。衛生工学屋さんには「簡単かな」って感じましたが、三つ書けと言われると、二つしか思い出せなかったりします。
回答案
問 2 有機溶剤について、以下の設問に答えよ。
(1)有機溶剤の物質としての特性について説明せよ。
・低沸点で揮発性が高い。
・脂溶性が高くいろんなものを良く溶かす。
・容易に燃焼し、引火点の低い物質も多い。
(2)職場において有機溶剤にばく露された際の吸収経路と排泄経路について説明せよ。
・蒸発した溶剤蒸気を吸引することで呼吸器から吸収される。
・脂溶性が高いため、皮膚からも吸収される。
蒸気(ガス)は、呼気で排出。
体内に吸収された場合、肝臓などで代謝されたり、そのままで尿からも排出される。
(3)有機溶剤が体内に吸収された後に、主に分布する臓器あるいは組織を三つ挙げよ。
(これは、難しいなあ)
肝臓・脂溶性が高いため、神経細胞にも吸収される。
脳を入れるか?
(4)有機溶剤に共通する毒性を三つ挙げよ。
急性毒性:麻酔作用、
慢性毒性:肝機能障害
あと共通するって、何だろう。 皮脂を溶かすので肌荒れ?
(5)以下の①~④の有機溶剤は、上記(4)の共通する毒性に加えて、特異的な毒性を有している。それぞれの有機溶剤の特異的な毒性(健康障害)を列挙せよ。
① 二硫化炭素 精神障害(せん妄・躁うつ)
② ノルマルヘキサン 抹消神経障害
③ ベンゼン 造血障害
④ メタノール 失明 (目散る)
②③はヘップサンダル事件と言って、この業界では歴史的に有名な事案です。
(6)有機溶剤には、有機溶剤中毒予防規則において「第三種有機溶剤等」に分類されるものがある。その性状を説明し、該当する有機溶剤の例を一つ挙げよ。
ガソリンや石油エーテルなどの石油製品
主成分は、長鎖アルカンの混合物
(7)有機溶剤には、特定化学物質障害予防規則において「特別有機溶剤等」に分類されるものがある。
① 「特別有機溶剤等」に分類される有機溶剤に共通する健康影響は何か。
発がん性
② 「特別有機溶剤等」に分類される有機溶剤を三つ挙げよ。
以下から、3つ
エチルベンゼン、クロロホルム、四塩化炭素、1,4―ジオキサン
1,2―ジクロロエタン、1,2―ジクロロプロパン、ジクロロメタン
スチレン、1,1,2,2―テトラクロロエタン
テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、メチルイソブチルケトン
(8)有機溶剤を常時取り扱う作業者に対して実施される生物学的モニタリングについて説明せよ。
実際のばく露量を把握し、早期に健康障害の発生を予防するために、作業中あるいは、作業後物質ごとに定められた時間以内に、採取した血液や尿を検査する。
検査対象物質は、有機溶剤そのものの場合と、その代謝物の場合がある。
(9)有機溶剤ばく露による健康影響を予防するための ①作業環境管理と ②作業管理について、それぞれ述べよ。
①作業環境管理:
有害物質が作業者に暴露するのを防止するため、有害物の隔離や発散防止など、主として工学的措置を取り、作業環境中の有害物質濃度を下げるなど、良い環境を維持して、作業者へのばく露を防止する管理方法
②作業管理:
適正な作業標準の設定、教育、個々の労働者に対する個別的な作業の指導などによって、適正な作業動作、機器の取り扱い、個人用保護具の使用方法などを習得させ暴露を防止する。


有機溶剤作業主任者技能講習 修了試験を突破(合格)するための本
- 作者: 津田 文男
- 出版社/メーカー:
- 発売日: 2019/07/15
- メディア: Kindle版
10月10日は「転倒予防の日」(再掲) [法令・通達情報※保健衛生]
職場での転倒予防に取り組みましょう!
・ 荷役作業時の墜落・転落災害の防止対策
・ ロールボックスパレット(カゴ車)の安全な取扱いの推進
・ 特に多発している転倒災害の防止対策
・ 高年齢労働者の労働災害の防止対策
・ 特に多発している介護中の腰痛や転倒による災害の防止対策
・ 高年齢労働者の労働災害の防止対策
10月10日は「転倒予防の日」 [法令・通達情報※保健衛生]
職場での転倒予防に取り組みましょう!
・ 荷役作業時の墜落・転落災害の防止対策
・ ロールボックスパレット(カゴ車)の安全な取扱いの推進
・ 特に多発している転倒災害の防止対策
・ 高年齢労働者の労働災害の防止対策
・ 特に多発している介護中の腰痛や転倒による災害の防止対策
・ 高年齢労働者の労働災害の防止対策
「脳・心臓疾患の労災認定基準を改正」が通知されました。 [法令・通達情報※保健衛生]
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21017.html
「脳・心臓疾患の労災認定基準を改正」が通知されました。
【認定基準改正のポイント】
■長期間の過重業務の評価に当たり、労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合評価して労災認定することを明確化
■長期間の過重業務、短期間の過重業務の労働時間以外の負荷要因を見直し
「休日のない連続勤務」、「勤務間インターバルが短い勤務」、「出張以外の事業場外の移動」、「心理的負荷を伴う業務(内容追加)」及び「身体的負荷を伴う業務」を新たに規定
■短期間の過重業務、異常な出来事の業務と発症との関連性が強いと判断できる場合を明確化
発症に近接した時期とは、発症前おおむね1週間
■対象疾病に「重篤な心不全」を追加
関連する、「労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項等に関する指針」についても、第3条の留意事項について、【平成十三年十二月十二日付け基発第一〇六三号】から、「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準について」(令和3年9月14日付け基発第0914第1号厚生労働省労働基準局長通達)に、変更されています。
9/14官報:労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項等に関する指針の一部を改正する件
従来からの基準となる過労働時間については、以下の通りで、基準を維持するという判断です。
※労働時間
・発症前1か月間に100時間または2~6か月間平均で月80時間を超える時間外労働は、発症との関連性は強い(※)
・月45時間を超えて長くなるほど、関連性は強まる
・発症前1~6か月間平均で月45時間以内の時間外労働は、発症との関連性は弱い
※労働時間以外の負荷要因
・ 拘束時間が長い勤務
・ 出張の多い業務 など
にほんブログ村
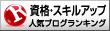
資格・スキルアップランキング
令和2年 労働安全衛生調査(実態調査) 結果の概況(その2) [法令・通達情報※保健衛生]
R2労働衛生調査結果レビュー
https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/r02-46-50b.html
事業所が行っている安全衛生管理、労働災害防止活動及びそこで働く労働者の仕事や職業生活における不安やストレス、受動喫煙等の実態について調査
事業所調査+個人調査を実施
〔メンタルヘルス対策(※)への取組状況〕
〔受動喫煙(※)〕
〔高年齢労働者に対する労働災害防止対策への取組状況〕
〔長時間労働者に対する取組〕
〔仕事や職業生活に関するストレス〕
〔受動喫煙(※)〕
<事業所調査>
〔メンタルヘルス対策(※)への取組状況〕
メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所の割合は 61.4%
(平成 30 年調査 59.2%) 横ばい
このうち、職場環境等の評価及び改善に取り組んでいる事業所の割合は 55.5%
(同 32.4%) 約1.5倍
〔受動喫煙(※)〕
屋外を含めた敷地内全体を全面禁煙にしている事業所の割合は30.0%
(平成30年調査13.7%) 増加(倍増以上)
〔高年齢労働者に対する労働災害防止対策への取組状況〕
60 歳以上の高年齢労働者が従事している事業所のうち、
高年齢労働者に対する労働災害防止対策に取り組んでいる事業所
81.4%
本人の身体機能、体力等に応じ、従事する業務、就業場所等を変更している事業所〔長時間労働者に対する取組〕
1か月間の時間外・休日労働時間数が
45 時間超 80 時間以下の労働者がいた事業所 16.3%[平成 30 年調査 25.0%]
80 時間超の労働者がいた事業所の割合は 2.5%[同 7.0%]
長時間労働者がいた事業所のうち、
面接指導の申し出があった長時間労働者に対する医師による面接指導の実施状況
面接を実施した事業所45 時間超 80 時間以下の労働者がいた事業所では
実施78.9%、
80 時間超の労働者がいた事業所では
実施95.4%
労働衛生のしおり 令和3年度 
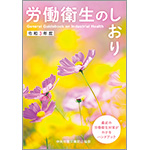
|
|













